Last Updated: March 30,2021
わが国でも年末になるとその1年間を振り返り、また新年に向けた取組み課題を公表するのがメディアの恒例であるが、米国の個人情報保護団体EPIC(Electronic Privacy Information Center)は、2005年12月30日に米国を中心としたプライバシー問題を簡潔・率直に総括し、また2006年の課題を要約している。
以下簡単に紹介するが、世界的なテロ対策の糸口が見えないなか本ブログでも数回紹介したとおり、欧米各国は取り締まり強化に向けプライバシー権より優先するかたちでの立法化が進みつつある。今回提示された問題はわが国の明日の問題かもしれない。
(1) 筆者ブログ「2001年愛国者法(PATRIOT Act)」 (筆者注4参照)問題
年末に連邦議会などで大論議を呼んだ時限立法である同法(注1)が、議会の承認と結論というかたちでなく、上院下院のリーダーの合意で一時的な延長(5週間)がまとまった。12月の議会では同法の承認をめぐる両院の改正案が議論の中心となったが、とりわけ上院案は監視強化に関する規定について難問を投げかけたものであった。激しい議論が2006年も引き続くであろう。
(2)個人の機密情報違反が増加
この1年、米国民5500万人以上をなりすまし詐欺の危険にさらす事件が130件発生した。犯人は、セキュリティへの取組みの脆弱性、悪意を持つ内部インサイダーまたある場合はなりすまし犯人に直接個人情報を販売した者である。これらの違法な行為は、取扱企業に消費者に今何が起きているかについての情報提供を義務付ける州の立法のみにより明確になるといえる。今年は連邦議会でこの問題をめぐりかますきびしい法案が出されたが、あるものは連邦レベルでの取組みを訴えるというプラス面もあったが、あるものは州による立法を排除したり、企業に対しプライバシーやセキュリティ面の失敗を隠す口実を与えるなどマイナスになったものもある。
(3)連邦国防総省(U.S.Department of Defense)のプライバシー無視
アンクル・サム(政府のこと)は、国民だけを欲しただけでなく、国民自身の情報を欲したのである。今年の初め、国防総省は学生情報の追跡と学生を軍隊に採用するため共同マーケテイングと採用に関するデータベースの構築を提案した。当該情報の内容は民族性、電話番号、e-mail アドレス、研究・クラブ活動分野に関するものであった。記録システムは学生の両親の軍隊の採用に関する姿勢なども含まれていた。結局、国防総省は明らかにプライバシー保護法違反となることから、公にする前に準備内容を明らかにした。
(4)連邦控訴裁判所(大法廷)がe-mailの盗聴法違反で好ましい判決
2005年8月11日、連邦第1巡回区控訴裁判所は、e-mailの内容を傍受することはコミュニケーションの仲介のみで盗聴違法には違反しないとした2004年6月29日の第1巡回区控訴裁判所の裁判官3人による合議決定を覆し、裁判官全員で本人がe-mailを受信する前に一時的にサーバーに格納することならびに保管場所の移動であっても、「盗聴法(Wiretap Act)」に違反すると判断した。
本事件については本ブログでは取り上げていないが、e-mailの盗聴行為と、盗聴法の解釈に関する重要判決であり、事実関係や裁判の経緯を含めEFF(Electronic Frontier Foundation)サイトの解説等に基づき補足する。
被告ブラッドフォード・カウンセルマン(Bradford Councilman)は本屋で、e-mailで顧客に対し販売サービスを行っていた。起訴状によると被告は従業員2人に対しメール処理用ソフトウェアを加工し、自身の競争相手である「アマゾン」からの全メールをひそかにコピーし、受信者たる顧客のメール口座に到達する前に被告のメールアカウントに送るよう命じた。
2004年6月29日の連邦第一巡回区控訴裁判所の合議結果では、被告がコピーしかつルートを変更したとき、電子的記憶装置に保存されていたもので、盗聴法にいう「傍受(intercept)」には該当しないとし、被告の責任を否定した。
これに対し、EFF等の人権擁護団体は政府に対し公聴会を要求、同裁判所は再審決定を行い、その結果は「メールは送信の間、一時的にコンピュータのメモリーに保存されるが、メール配信業者やその他の者が秘密裡に傍受する行為は同法にいう犯罪行為である」と判示した。
この問題は2004年判決がいみじくも述べているとおり「盗聴法の立法趣旨が技術進歩で骨抜きにされた」といえる。
(5)有権者のプライバシー問題
政府機関が電子投票システムのガイドラインの内容で今年注目を集めた問題である。このシステムは投票内容の機密性を保存する一方で、その手続きのオープンな監査を認めるというのが電子投票制度の基本であった。また、有権者のプライバシーはジョージア州の判決で勝ち得られた。そのケースでは投票所で州が発行した写真IDの提示を定めた州法は憲法違反であるとされた。選挙人登録を減らすことにつながらなかった。このID法は、貧困層、高齢者、少数派の人々をがっかりさせたといえよう。
(6)連邦国務省(U.S. Depratment of State)はハイテク技術を踏まえたパスポート計画を中止したが、なお課題は残る
国務省はその分野の専門家から小型のIDタグを備えたパスポートは海外を旅行する米国人が標的の的になるという指摘を受けて原案を修正し、セーフガード対策を加えたが、専門家からはなお脆弱性が残ると指摘されている。移民書類、政府発行ID、クレジットカード、その他さまざまな消費者向け商品や梱包にチップを埋め込む計画が進んでいる。
(7)消費者信用凍結法(注2)の利用が拡大
なりすまし詐欺は単に本人の個人情報が盗まれるという問題だけでなく、債権者が相手が誰かを十分に確かめずに口座情報を提供するという問題でもある。ニューヨーク州とメリーランド州などはこの問題について、本人の許可なしに貸付事業者が新規口座の開設を行うことを中止させる内容の法律を定めた。
(8)「2005年REAL ID 法」の行方は
2005年に連邦議会は好調貸しや投票もなしに州の運権免許証を国民IDカードに替えるという法案を静かに通過させた。REAL ID法(Pub. L. 109-13 REAL ID ACT OF 2005 )に反対する立場の人々は協力を強化しており、国土安全保障省(DHS)は市民に対して「意見をどうぞ」となったときには厳しい戦いになろうと予想している。(わが国の”Real ID Act”解説)
(9)「米国にようこそ」「まず指紋をお願いします」
米国は観光客を中心に 指紋情報の収集を急速なペースで拡大している。「US-VISIT プログラム」(注3)は米国を訪れる観光客などは指紋の持参が義務付けられる。しかし、指紋認証の誤り、指紋スキャナーの騙しやすさは、なお指紋IDシステムを苦しめ続けることになろう。
(10)学生のプライバシー問題
RFIDの問題はプライバシー問題の最前線の話題となっている。RFIDメーカーはスパイ・チップを埋め込んだ学生IDカードの強制化を強く学校に働きかけている。金属探知機、ビデオカメラ、その他の侵入行為による第三者へのマーケテイング活動や新規採用をめぐる動きが普通になっている。それに対し、学生や両親は抵抗している。2004年にカリフォルニア州の「スパイチップ計画」は失敗し、両親たちは2006年の国防総省(DOD)の新人募集のデータベースの構築反対に結集した。
(11)位置の追跡(location tracking)問題
港や英国のハイウェイの管理者は交通の流れを測定し、混雑の緩和を行うことを意図しているが、道路使用税の徴収を狙っている。これは、道端のナンバープレーのリーダーやドライバーが電話する信号の動きを追跡することに基づく。いくつかのプログラムは、個人を特定するデータの自動追尾機能を削除するが、「終わりの見えない展開」の適用において捜査当局は捜査手段として携帯電話の追跡の多くを利用していることを示す。
(12)政府のデータマイニング(注4)に関する新たな示現
つい先日、ジョン・ポインデクスターの全情報認知システム開発プログラムが終了を迎えた。しかし、連邦政府は、このシステムをあきらめていない。2006年に政府のデータマイニングの範囲と民間部門が保有している米国市民情報の量に関して驚異的な示現が出てこよう。
(13)DNAデータベースと遺伝子のプライバシー問題
筆者追記:EPICが””Genetic Privacyと題して、これまでの裁判所の判断を詳しく解説している。
(14)個人情報データブローカーの規制
なりすまし詐欺の増加や損失額は500億ドルを超えている。2006年にはデータブローカーの扱いについての立法がなされると見込まれているが、立法担当者の関心は、データの漏洩の内容の公開を義務付けるだけでなく、多くはほとんどが法的に規制されないデータブローカーの存在そのものの見落としが問題となっている。
***********************************************************************************
(注1)Patriot Actは正式名は、”Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT ACT) Act of 2001”である。
(注2)米国の一部の州で制定されているもので、2005年12月8日施行された「ニューヨーク州情報セキュリティ侵害通知義務法(Information Security Breach and Notification Act)」(section 208 of the State Technology Law and section 899-aa of the General Business Law)は、カリフォルニア州のセキュリティ侵害通知法に似ており、企業および州機関に「暗号化されていない個人情報が権限のない人に取得されたおそれのある」住民への通知義務があると規定し、個人情報が漏れたおそれがあるときは、本人にその事実を通知することを流出元に厳格に義務づけている。同州の司法長官府の解説参照。同州情報技術局(New York State Office of Information Technology Services :ITS)の解説も参考となる。
(注3)「US-VISIT プログラム」は、米国の出入国システムの強化を目的とした国土安全保障省のプログラムである。同プログラムにより米国は、入国する訪問者の身元確認およびビザ・出入国規則遵守の確認を効果的に行うことが可能になるとされている。DHSの解説
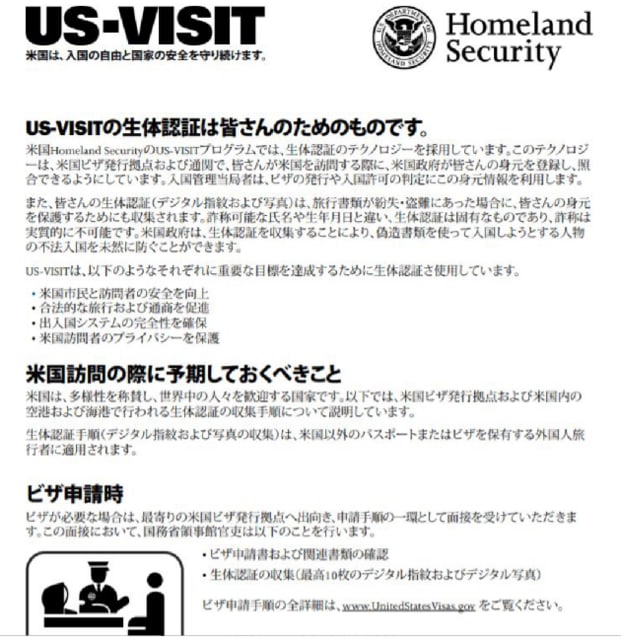
(https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/usvisit/usvisit_edu_traveler_brochure_printer_friendly_japanese.pdf)
(注4)小売店の販売データや電話の通話履歴、クレジットカードの利用履歴など、政府機関・企業に大量に蓄積されるデータを解析し、その中に潜む項目間の相関関係やパターンなどを探し出す技術。
〔参照URL〕
http://www.epic.org/alert/EPIC_Alert_yir2005.html
***********************************************************
(今回のブログは2005年12月31日登録分の改訂版である)
Copyright © 2005-2010 芦田勝(Masaru Ashida).All Rights Reserved.No reduction or republication without permission.

コメント
コメントを投稿